この記事は、こういった方に向けた記事です↓
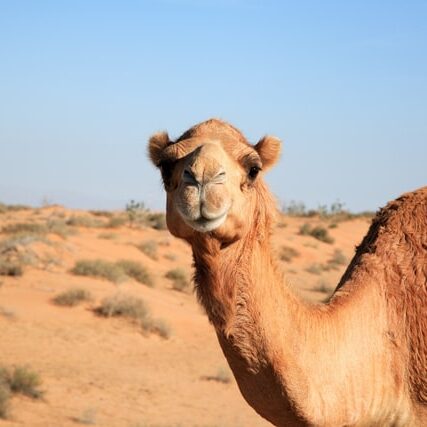
一級建築士の法規を時間内に解き切れない・・・
法令集を引きすぎている気がする。
- 法文の内容ではなく法文の位置を覚えた方が良い理由が分かります。
- 建築基準法の構成をカンタンに説明します。
- 法令集の構成を効率よく覚える方法を説明します。
この記事の筆者は、2020年の学科試験で105点(125点満点)を獲得し、合格しています。合格点は88点でしたので、17点の余裕をもって合格しています。
学習期間は1年程度。
初年度の製図試験は不合格。2回目の製図試験で2021年に合格しました。
独学での勉強だと不安がある人には、以下の記事が参考になります。
10万円以下の通信講座もあります。
<一級建築士を目指している方↓>

<二級建築士を目指している方↓>

法文の内容ではなく代表的な法文の位置を覚えた方が良い理由
一級建築士試験の法規で最終的に目指すべき、最も効率の良い解き方は、以下の解き方です。
- 「暗記すべき項目」(←少ない)はすべて暗記し、法令集を引かずに選択肢の正誤を判断する
- それ以外の項目は、問題の4つの選択肢のうち、正答肢っぽい選択肢の1つか2つに当たりをつけ、怪しいものから法令集を引いて確かめていく
一級建築士の法規の試験は時間がギリギリに設定されているため、すべての選択肢を法律で確認していたら時間が足りなくなってしまいます。
そのため、最低限の、暗記しやすく点数を取りやすい項目は、内容を暗記することで、法令集をほとんど引かずに解きます。(詳細:一級建築士の法規を法規を【暗記】で攻略する方法)
しかし、法規の試験の問題の大部分は、暗記のみで対応しようとすると引っ掛かってしまうような引っ掛け問題や、暗記した知識のみでは対応きないような問題です。
そのため、正答肢を確かめるために、1問につき1つか2つの選択肢に対して法令集をひくのが最も確実な解き方です。
ここで、代表的な法文の位置を覚えておくことで、法令集を引く時間を短縮できるので、時間に余裕を持てるようになり、焦って法文を読んだために読み落としが発生したりするのを防ぐことができます。
法令集に乗っている法文は、ある程度規則性をもって並べられているため、法文の内容を覚えるよりも、代表的な法文の位置をなんとなく覚える方がはるかに簡単です。
逆に法文の位置を全く覚えていないと、時間が足りなくなったり焦りで重要な法文を読み落としてしまったりします。
【超基本】法律と施行令の構成
- 一番最初にあるのが法律。法律の中だけでは定めきれなかった詳細な基準が、施行令に収録されている。
- 全ての施行令の条文には、元となる法律の条文がある
法律が親で、施行令が子みたいな感じです。
別の言い方をすれば、法律が幹で、施行令が枝のようなイメージです。
(※例外として、例えば階段の蹴上寸法の規定は、法律ではなく施行令からしか探せない。←法律36条から飛んでくる条文です。法律36条は「この章で定めきれなかった決まりは施行令で定めます」といった内容です)
原則として、問題を解くために法令集を引くときは、まずは施行令ではなく法律の中から条文を探し、法律の注釈から施行令の該当ページに飛ぶのが〇です。
実際には、問題演習をしていく中で何度も引くような、よく使う施行令の条文は、法律からではなく直接施行令から探したほうが早いような場合が多いです。
しかし、初めて引くような条文は、まずは法律から探し、法律の注釈から施行令の該当条文に飛んだ方が、正確に早く解ける場合が多いです。(法律の、見落としやすい位置に重要な条文があったりするため)
法令集の構成(法文の位置)を効率よく覚える方法
法令集を引くときに一番速く引けるのは、インデックスと、指で覚えた法令集の厚さの感覚から、知りたい条文が書いてあるページにたどり着くことです。(よく使う条文を探すときに使う)
あまり使わない条文を探すときは、該当条文と思わるる条文をまず目次から探し、実際にページを開いて確かめます。
インデックスや目次から、目的の条文にたどり着けるようになるため、↓の作業を行います。
- 次章を読んで、法令集の構成をざっくりイメージできるようになるまで頭に入れる。
- 実際に法令集を引きながら問題を解いていく過程で、法令集に貼ってあるインデックスと、法文の内容をリンクさせる
- 実際に法令集を引きながら問題を解いていく過程で、目次と、法文の内容をリンクさせる
- 実際に法令集を引きながら問題を解いていく過程で、目当ての情報(よく使う情報)が 法律・施行令・別表 のうちどれに書いてあるのかを覚えていく
法令集の構成をざっくりイメージできるようになるまで頭に入れる。
次章に、法律と施行令の各章にどんな法文が収録されているかをざっくりまとめましたので、それを読んで、法令集の全体の流れや構成をざっくり理解してください。
調べたい条文が、どの章に載っているか予想できるようにしましょう。(「完璧に」ではなく、「ざっくり」でOK)
法令集に貼ってあるインデックスと、法文の内容をリンクさせる
実際に法令集を引きながら問題を解いていく過程で、インデックスと、法文の内容をリンクさせましょう。
よく使う条文について、「〇〇の情報を調べるためには△△のインデックスが張ってあるページを開けばよい」ということが分かるようになるのが目標です。
(例:防火地域内で耐火建築物としなければならない建築物の種類をしりたい→施行令の「防火地域」のインデックス・・・etc.)
目次と、法文の内容をリンクさせる
調べたい条文がどこにあるかわからないときは、まずは目次から探しましょう。
調べたい内容が書いてある条文を、目次から探せるようにするのが重要です。
実際に法令集を引きながら問題を解いていく過程で、「〇〇の情報を調べたいから、目次の△△のページを開いたら良さそう・・・」のような感覚を磨いていきましょう。
目当ての情報(よく使う情報)が 法律・施行令・別表 のうちどれに書いてあるのかを覚えていく
前章で「原則、まずは法律の中から目当ての情報を探して、注釈から施行令に飛ぼう」とか言いましたが、よく使う条文については、法律・施行令・別表のうちどれに書いてあるかを覚えておいた方が早いです。
例えば、防火地域・準防火地域内で耐火建築物としなければならない建物の種類を調べるためには、いきなり施行令から探した方が早いし、一種住居地域内に工場を建築できるかどうかを調べるには、いきなり別表2を見た方が早いです。←次章でも紹介します。
このように、よく使う条文については、「〇〇の情報を探すには施行令をみる」のように決めておいた方が良いです。
それでも該当の条文が見つからなかったときには、原点に戻り、法律の目次から順番に探していくようにしましょう。
建築基準法の構成とポイントをカンタンにざっくり紹介します
まず、ひとまず押えてほしいところを超カンタンにまとめます。
施行令は、基本的には法律の注釈から飛ぶことができる場合が多いため、法律から飛びにくい規定に絞って紹介します。
- 1章 法律の目的、用語の定義、手続き関係のルール
- 2章 建物単体の衛生、地震対策、火事対策のルール
- 3章 まちづくりや地域の住環境を守るためのルール(高さ制限や面積の制限)
- 4章 建築協定
- 6章 雑則(仮設建築物、既存不適格、用途変更、消防同意)
- 1章 用語の定義、面積や高さの算定、手続き関係のルール
- 2章 一般構造(天井・床の高さ、地階の防湿、階段寸法)
- 4章 耐火構造、耐火性能、不燃性能、防火設備、防火区画、その他区画関係
- 5章の3 避難安全検証法
次に、建築基準法と施行令の全体の構成を、もう少し詳細にまとめました。
「構成を覚える」のが難しいという人は、「順番をなんとなく覚える」「建築基準法と施行令のどちらに書いてあるかを覚える」といった意識でやってみても良いです。
※よく使う法文には黄色のアンダーラインをします
※法律ではなくいきなり別表や施行令を見た方が早いものは赤字
1章 法律の目的、用語の定義、手続き関係のルール
- 1条 法律の目的
- 2条 用語の定義←※重要。収録されている用語に何があるか覚えておく。
- 3条~18条の3 手続きのルール、判定機関や行政庁のルール
6条=確認申請←暗記で対応。別表1は見てもよい。12条=定期報告
2章 建物単体の衛生、地震対策、火事対策のルール
- 19条 敷地の衛生と安全
- 20条 地震対策
- 21条~27条 火事対策(火事になりにくい建物のつくりなど)
- 28条~31条 衛生(有害物質対策や採光、換気等)
28条=採光、換気、28条の2=シックハウス(有害物質)対策、30条=共同住宅、長屋の界壁 - 32条~34条 設備
- 35条~35条の3 火事対策(避難)
3章 まちづくりや地域の住環境を守るためのルール
- 41条の2 この章の規定は都市計画区域、準都市計画区域内でのみ適用する←※重要
- 42条~45条 道路
- 46条~47条 壁面線
- 48条~58条 建物の用途の制限
- 52条~54条 建物の面積と敷地の面積に関する制限(建蔽率、容積率など)←暗記で対応。法文はあまり読まない
- 55条~56条 建物の高さの制限
- 61条~66条 防火地域、準防火地域
- 68条の2~68条の8 地区計画
3章の2 型式認定
- 68条の10~68条の26 型式認定
4章 建築協定
- 69条~77条 建築協定
4章の2、4章の3 建築基準適合判定資格者関係
5章 建築審査会
6章 雑則
- 84条の2~86条 仮設建築物や伝統的建築物等の緩和規定
85条 仮設建築物の緩和 - 86条の7 既存不適格建築物の緩和
- 87条 用途変更確認申請
- 87条の4、88条 建築設備、工作物の確認申請
- 89条~90条の3 工事現場、工事中の安全対策
- 93条 消防同意、消防通知
7章 罰則
別表1 耐火建築物としなければならない特殊建築物
別表2 用途地域内の制限
別表3 道路斜線制限(高さ制限)
別表4 日影高さ制限
1章 用語の定義、面積や高さの算定、手続き関係のルール
- 1条 用語の定義←※重要。収録されている用語に何があるか覚えておく。
- 2条 面積や高さの算定←※重要。収録されているものに何があるか覚えておく。
- 11条~16条 手続き関係
11条=中間検査、13条=検査を受けるまでの使用制限、16条=定期報告
2章 一般構造 建物使用時の安全性や衛生・健康被害対策
- 19条~20条の9 採光、換気、シックハウス(有害物質)対策
- 21条~22条の2 天井、床の高さ、地階の防湿
- 22条の3 共同住宅や長屋の界壁の構造
- 23条~27条 階段
- 28条~35条 便所、浄化槽
3章 構造強度
- 36条~36条の2、81条 構造計算ルートなどの選定方法
- 37条~39条 全構造で共通の項目(基礎と屋根ふき材等)
- 40条~80条 構造種別ごとの仕様規定(部材の寸法の最低値など)
- 82条~82条の6 構造計算の仕方
- 83条~88条 構造計算における外力や荷重の設定方法
- 89条~98条 材料種別ごとの許容応力度、材料強度
4章 耐火性能、防火区画
- 107条~111条 耐火構造、耐火性能、不燃性能、防火設備
- 112条~114条 防火区画、その他区画関係
5章 避難施設等(2方向避難、排煙設備など)
- 116条の2 この章が適用される居室
- 117条~126条 建物内の避難経路関係
- 126条の2~126条の3 排煙設備
- 126条の4~126条の5 非常用照明
- 126条の6~126条の7 非常用の侵入口
- 127条~128条の3 敷地内通路(地下街の通路についての規定も)
5章の2 内装制限 ←暗記が望ましい。128条の4第一号の表のみ見てもよい。
5章の3 避難安全検証法
5章の4 建築設備
- 129条の2の3~129条の2の6 設備(給排水、換気等)
- 129条の3~129条の13の3 エレベーター(非常用エレベーターも)
6章 用途制限
7章 高さ制限
7章の2 防火地域と準防火地域
7章の3 地区計画
8条 既存不適格への緩和等
- 137条~137条の17 既存不適格への緩和等
- 137条の18 用途変更確認申請が不要な類似の用途
9章 工作物の確認申請など
10章 雑則
- 144条の4 法42条1項5号の道の基準
- 145条 道路内建築の基準
- 146条 建築設備の確認申請
問題を解いていて法文の場所の見当がつかないときは、目次を見る!
法令集の構成をいくら覚えても、問題を解くための根拠となる法文の場所の見当がつかないこともあります。
そんな時は、以下の順番で探すと探しやすいです。
- 法律の目次から、怪しそうなページを探す
- 目次で探したページの法文を読む
(それでもダメなら・・・) - 施行令の目次を見て、怪しそうなページを探す
- 目次で探したページの法文を読む
※怪しそうなページが見つからないときは、「用語の定義」から探してみる(基準法2条、基準法施行令1条)
※どこにあるかわかりづらい法文は「雑則」の章に載っていることも多い(建築基準法第6章、基準法施行令第10章)
(参考)法令集の構成を覚えても場所を探しにくい条文は、マーキングで対応します
法令集の構成をある程度覚えても、場所を探しにくい条文があります。
規則的に並んでおらず変な場所にある条文などです。
こういった条文は、法令集にマーキングして目立たせることで、探しやすくしたり見落としにくくしたりします。
詳細:一級建築士の法規を時間内に解くには法令集にマーキングを!
独学に行き詰った人へ:おすすめの予備校(10万円以下の講座もあります)
独学だと不安な人、独学に行き詰った人は、予備校や通信講座の利用も検討してみましょう。
安いものだと10万円以下で受けられる講座もあります。
予備校、通信講座の選び方は以下の通りです。
- 講座の質
- 金額の安さ
- 勉強時間の確保のしやすさ
詳細:【一級建築士】好コスパおすすめ通信講座・予備校を比較(ランキングで紹介)
まとめ
- 法令集に貼ってあるインデックスと、法文の内容をリンクさせよう
- 目次と、法文の内容をリンクさせよう
- 調べたい法文がどの章に収録されているか予想できるようになろう。
独学での勉強だと不安がある人には、以下の記事が参考になります。
10万円以下の通信講座もあります。
<一級建築士を目指している方↓>

<二級建築士を目指している方↓>




コメント